子犬を迎えたばかりの飼い主にとって、「落ち着きのない子犬のしつけ」は大きな悩みのひとつです。とくにトイプードルやチワワなど活発な犬種では、思った以上にやんちゃな行動に戸惑うこともあるでしょう。「犬 落ち着きがない 性格なのかな?」「この状態はいつまで続くの?」と感じている方も少なくありません。
噛む、吠える、じっとしていられないなどの行動は、成長過程の一部であることもあれば、飼い方や接し方に原因がある場合もあります。また、まれに病気が関係していることもあるため、落ち着きのなさの理由を正しく見極めることが重要です。
本記事では、「子犬が狂ったように噛むときの対策」や、犬種別の特徴、「やんちゃな子犬がいつ頃落ち着くのか」といった疑問に答えながら、初心者でも実践しやすいしつけの方法をご紹介します。おすわりなどの基本トレーニングも含め、なぜその行動が起きるのか、どう対処すればよいのかを具体的に解説します。
- 子犬が落ち着かない原因と性格の関係
- 噛むなどの問題行動への具体的な対策
- トイプードルやチワワなど犬種別のしつけ傾向
- 初心者でも取り組めるしつけの方法と工夫
落ち着きのない子犬へのしつけの基本とは
原因と性格的特徴を理解する

結論として、子犬が落ち着きなく見えるのは「性格」と「発達段階」の影響が大きいと考えられます。さらに、周囲の環境や接し方によって、その傾向は強まることがあります。
理由は、子犬の脳や神経系はまだ未発達であり、外部からの刺激に対して強く反応しやすいためです。また、一部の犬はもともと活発な性格であることから、同じ月齢でも行動の差が出やすくなります。
例えば、トイプードルやチワワのような小型犬は、人間と遊ぶのが大好きな一方で、刺激に対して敏感に反応しやすい傾向があります。室内で聞こえる音、見慣れない物、急な動きなどが、落ち着きのなさに拍車をかけている可能性もあります。
このような性格や発達上の特性により、「常に動き回っている」「噛む」「吠える」といった行動が見られることが多いです。しかし、これらは異常ではなく、成長の一環としてとらえることが重要です。
一方で、こうした行動が強く、長期間にわたって続く場合には、生活環境の見直しや獣医師への相談も視野に入れるべきです。場合によっては、過剰なストレスや病気のサインであることもあるためです。
まずは「うちの子は落ち着きがない」と感じても、年齢・性格・生活環境のバランスを見ながら冷静に観察することが第一歩ではないでしょうか。
いつ頃落ち着く?成長段階の目安
多くの場合、子犬が落ち着いてくるのは生後6ヶ月~1歳ごろとされています。ただし、個体差や犬種によって異なるため、目安としてとらえることが大切です。
理由として、脳の発達やホルモンバランスが徐々に安定し、自制心や学習力が高まる時期がこの頃に重なるからです。加えて、しつけの積み重ねが定着してくる時期でもあるため、行動に変化が見られやすくなります。
例えば、8週間齢で迎えた子犬が、最初は家具を噛んだり部屋中を走り回ったりしていたのに、生後7~8ヶ月には落ち着いておすわりや待てができるようになる、というケースはよくあります。
ただし、これには日々の接し方や環境づくりも深く関係しています。社会化が不足していたり、ストレスの多い環境にいる子犬は、成長しても落ち着かないままになることがあります。
また、小型犬は大型犬に比べて精神的な成熟がやや遅れる傾向があるため、トイプードルなどでは1歳半くらいまではやんちゃな性格が続くことも珍しくありません。
このため、「いつになったら落ち着くの?」と焦らず、月齢に応じて適切な対応を重ねていくことが、健やかな成長と安心できる関係づくりにつながるのではないでしょうか。
噛む癖・暴れる行動の理由と対策

まず知っておきたいのは、子犬の噛む行動や暴れるような動きには、発達上の理由があるということです。これは問題行動というよりも、学習の一環である場合が多いです。
というのも、子犬は「口を使って物を確認する」習性があります。人間の赤ちゃんが手で物を触るのと同じように、犬の場合は口がその役割を果たしています。また、歯の生え替わり時期(生後3~6ヶ月頃)は口の中がムズムズするため、何かを噛みたくなるのです。
加えて、エネルギーが有り余っていると、家具やカーペットを噛んだり、突然走り回ったりすることがあります。これは、運動不足や刺激不足によるものと考えられます。
具体的な対策としては、噛んでも良いおもちゃを与えることが第一です。例えば、凍らせたガムタイプのおもちゃや、知育トイを活用することで、自然にエネルギーを発散できます。さらに、1日10分でも構いませんので、遊びやトレーニングの時間を意識して取り入れることが有効です。
注意点として、叱るだけの対応は逆効果になりやすいです。大声や手を叩くと、犬が不安や恐怖を感じ、より興奮する原因になってしまいます。代わりに、噛んでほしくない物に対しては無反応を貫き、適切なものに噛み替えさせるという方法が効果的です。
こうした習慣はすぐには変わりませんが、落ち着いた対応と一貫したしつけを続けていくことで、徐々に改善していくでしょう。
トイプードルやチワワなど犬種ごとの傾向
犬種によってしつけのしやすさや行動の傾向が異なることは、意外と知られていません。トイプードルやチワワなどの人気犬種にも、それぞれ特徴があります。
トイプードルは非常に賢く、しつけに対する理解力が高い犬種です。人の表情や声のトーンをよく読み取るため、トレーニングの反応も早い傾向にあります。その反面、甘やかしすぎると「人の指示よりも自分の気持ちを優先する」ような行動が目立つことがあります。
一方のチワワは、体は小さくても自己主張が強く、警戒心が高い性格です。初対面の人や音に敏感で、吠え癖がつきやすいのが特徴です。そのため、しつけはできるだけ早い段階で始め、社会化をしっかり行う必要があります。
それぞれの犬種が持つ本来の性格や特性を理解した上で、しつけ方法を調整することが大切です。トイプードルであれば褒めて伸ばす方法が合いやすく、チワワの場合はルールを一貫して伝えることが重要です。
また、両犬種とも室内犬として人気がありますが、飼い主との距離が近くなる分、依存傾向が強まりやすい面もあります。常に一緒にいないと落ち着かない状態にならないよう、一定の距離感を保つことも意識したいところです。
こうした犬種ごとの特徴を踏まえて対応すれば、無理なく信頼関係を築けるようになるのではないでしょうか。
病気が原因の落ち着きのなさを見分ける方法

落ち着きのない行動がすべて「性格」や「成長過程」のせいとは限りません。場合によっては病気や身体的不調が関係しているケースもあるため、注意が必要です。
たとえば、頻繁に落ち着きなく歩き回る、眠れずに何度も姿勢を変える、急に暴れるような様子が見られるときには、何かしらの体の違和感を訴えている可能性があります。特に、トイレの失敗が増えたり、触られるのを極端に嫌がったりする場合は、痛みを抱えていることも考えられます。
実際、落ち着きのなさの背景に「皮膚のかゆみ」「耳の感染症」「消化不良」などが隠れていることがあります。こうした症状は行動の変化として表れやすく、早期発見の手がかりになります。
また、過度な興奮や攻撃性が急に現れた場合には、ホルモンバランスの異常や神経疾患も否定できません。このようなときには、すぐに獣医師に相談することが大切です。診断を受ければ、不安の原因が明確になり、対応も取りやすくなります。
見極めのポイントは、「以前と比べて急に変わったかどうか」「生活環境が変わっていないのに落ち着かない行動が続くか」です。これらが当てはまる場合は、体調チェックを優先したほうがよいでしょう。
しつけで改善しない落ち着きのなさがあるときは、まず体の健康状態を疑ってみてください。無理に矯正しようとする前に、体調を整えることが結果的に落ち着きを取り戻す近道になるかもしれません。
落ち着きのない子犬へのしつけ成功への近道
初心者でも実践しやすい方法

しつけは特別なスキルが必要だと思われがちですが、初心者でも実践しやすい方法はたくさんあります。大切なのは「短時間でも継続できる」「愛犬にとってわかりやすい」トレーニングを選ぶことです。
まず試してほしいのが、「おすわり」や「待て」といった基本のコマンドを使ったトレーニングです。これらは日常生活に取り入れやすく、成功体験を積ませやすいため、犬との信頼関係を築くうえでも有効です。1回の練習時間は5分程度でも十分で、遊びの延長で行えるのがポイントです。
次に、「褒めるタイミング」を明確にすることも大事です。できた瞬間に「いい子!」と声をかけ、おやつを与えることで、犬は「これをすると良いことがある」と学習します。タイミングが遅れると伝わらないため、反応は素早く行いましょう。
また、生活リズムに合わせてルールを決めるのも効果的です。たとえば、「飼い主の目が合ってからケージから出す」などの小さな決まりを作るだけでも、犬は落ち着いた行動をとりやすくなります。時間が取れない人でも、ルーティン化すれば無理なく実践できます。
注意点としては、しつけ中に叱りすぎないことです。失敗しても静かに無視するなど、感情をぶつけない対応が基本です。強い言葉や態度は、犬にとって混乱や恐怖の原因になりかねません。
このように、初心者であっても「短時間・明確なルール・褒める習慣」の3つを意識することで、無理なくしつけを始めることができるはずです。日々の積み重ねが、犬との安心できる暮らしにきっとつながっていくでしょう。
おすわりトレーニングを成功させるコツ
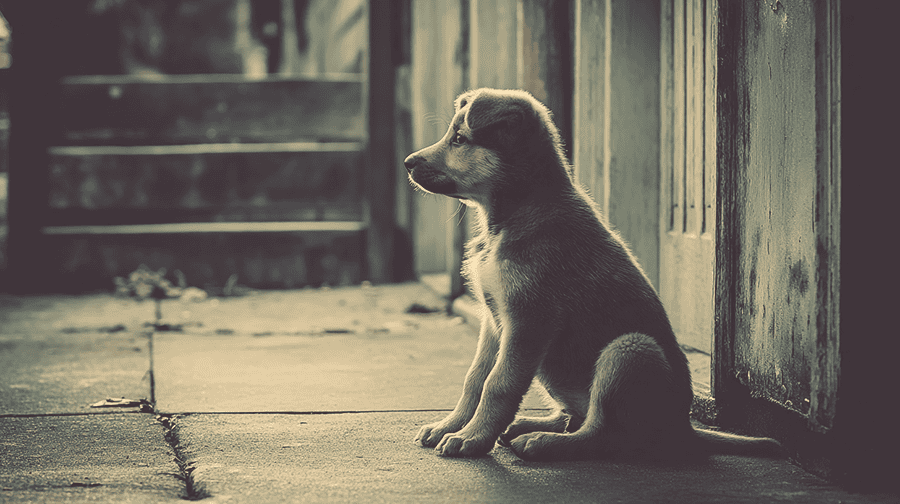
おすわりのトレーニングは、子犬との関係づくりの第一歩として非常に効果的です。落ち着いた行動を引き出す基本のしつけでもあるため、ぜひ早い段階から取り組みたいところです。
このとき大切なのは、「やり方」と「タイミング」を明確にすることです。中でもポイントになるのは、行動を誘導しやすい姿勢と、成功体験を積ませる工夫です。
まず、トレーニングの前には犬の注意を自分に向けさせましょう。名前を呼んでアイコンタクトが取れた状態から始めると、犬も集中しやすくなります。その上で、おやつを持った手を犬の鼻先から頭上に移動させると、自然と後ろに重心が下がり、お尻が床につきます。この瞬間に「おすわり」と声をかけましょう。
成功したらすぐにごほうびを与えます。最初は毎回褒めておやつを渡すことで、「座る=いいことがある」と犬に覚えてもらうことが重要です。数日繰り返すと、徐々に声の指示だけで座るようになってきます。
注意点としては、怒らないことです。座らなかったときに叱ると、犬は「おすわり」が嫌なことと結びつけてしまう可能性があります。また、トレーニングは長くても1回5分以内にとどめるのがよいでしょう。飽きてしまうと逆効果になるためです。
このように、楽しく短時間で終わる練習を繰り返すことで、子犬は自然に「おすわり」を身につけていきます。毎日の生活に取り入れながら、焦らずコツコツ続けてみてください。きっと成長と共に、落ち着きのある行動へとつながっていくはずです。
落ち着きのない子犬のしつけのポイント総まとめ
ここまでの大切なことをまとめると以下になります。
- 子犬が落ち着かないのは性格や成長段階による影響が大きい
- 飼い主の接し方や反応が子犬の行動に影響を与える
- 月齢とともに自然に落ち着いてくることも多い
- 適切な生活環境の整備が行動の安定につながる
- 多くの子犬は生後6ヶ月~1歳で落ち着き始める傾向がある
- トイプードルは賢く覚えが早いが依存心が強め
- チワワは警戒心が強く社会化不足が問題行動につながりやすい
- 噛み癖は口を使って学ぶ発達段階の一部である
- 過度な興奮や暴れ方には運動不足や刺激不足が関係する
- 噛む対象をおもちゃに誘導し、正しい行動を促す
- 行動が急変した場合は病気の可能性も視野に入れる
- 初心者でもできるトレーニングは短時間の繰り返しが基本
- 毎日の生活の中にしつけを組み込むことが成功のカギ
- おすわりトレーニングは手の動きとタイミングが重要
- 成功時の褒め方と報酬の与え方が定着率を左右する
